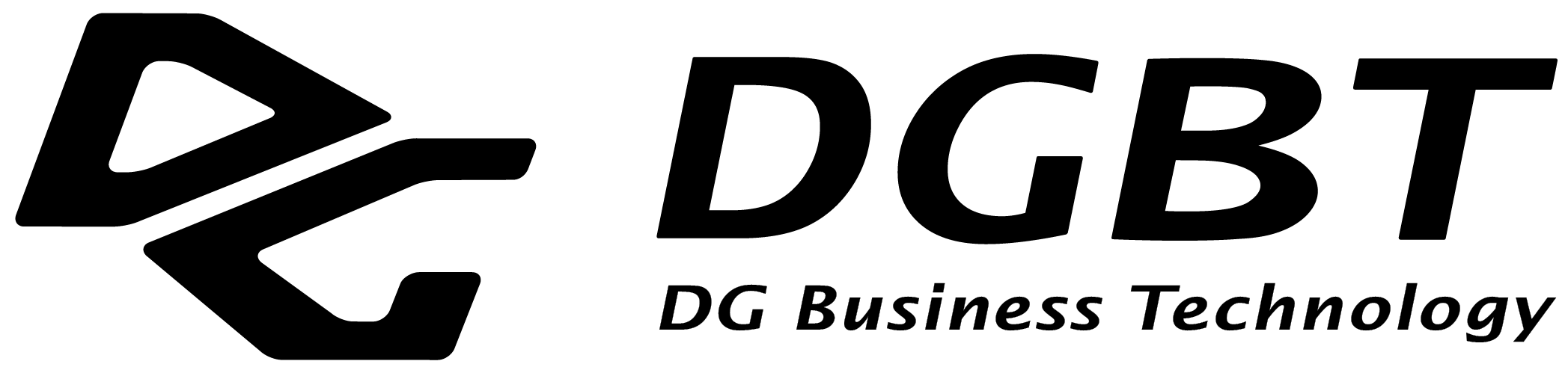ECレコメンドエンジンの基礎知識|売上向上につながる手法と導入メリットを解説

ECサイトで頻繁に目にする「こちらの商品もおすすめです」や「この商品を買った人は他にもこんな商品を購入しています」といった表示。これは「レコメンド(recommend)」と呼ばれ、ECサイトの"買いやすさ"や顧客体験の向上には欠かせない要素となっています。
本記事では、ECサイトがレコメンド機能を導入するメリットや、レコメンドロジックの種類、導入時の注意点ついて詳しく解説します。ECサイトの売上向上と顧客満足度アップを目指す方は、ぜひ参考にしてください。
レコメンドエンジン・レコメンドサービスとは?
レコメンドの基本的な定義とECサイトにおける役割
レコメンドとは「おすすめ」「推薦」という意味を持つ言葉です。EC・デジタルコンテンツサイトでは、ユーザの閲覧や購入などの行動履歴や属性データをもとに、それぞれに最適な商品をサイト上で動的に提案することを”レコメンド”と呼んでいます。ユーザーがECサイトで商品を閲覧・購入する際の行動パターンを分析し、他のユーザーにも関連性の高い商品を提案することで、クロスセルやアップセルの機会創出につなげるのがレコメンドの役割です。
ユーザー視点では自分の興味や好みを理解して商品を提示してくれるため、新しい商品の発見や選択のストレスが軽減され、サイトの利便性や信頼性が大幅に向上します。現代のECサイトにとって、レコメンド機能は競合他社との差別化を図る重要な要素となっています。
レコメンドの主なロジック・種類
レコメンドには複数のオススメのアプローチが存在します。以下より、代表的な手法を詳しく見ていきましょう。
協調フィルタリング
協調フィルタリングは、顧客の行動履歴(商品の閲覧・購入データ)を分析して、商品間の関連性を計算し、レコメンドを行う手法です。
「この商品を買った人は、こちらも購入しています」という形で関連商品を提案する仕組みで、例えばスマートフォンの購入者にスマホケースや保護フィルムを、プリンター購入者にインクカートリッジやコピー用紙をおすすめするといった具合です。
同じ商品を購入する人は似た購買行動を取るという前提に基づいており、シンプルなロジックながら高い効果を発揮するため、多くのECサイトで採用されています。また、ECサイト以外にもキュレーションサイトや動画配信サイトなど幅広い分野で活用されており、レコメンド機能の代表的な手法となっています。
協調フィルタリングにも、閲覧ベース(一緒に見ているもの)、購入ベース(一緒に買っているもの)があり、サイトの取り扱い商品やユーザの行動によってレコメンドされる商品は変化します。 協調フィルタリングの弱点は、十分な行動履歴データが蓄積されるまでは適切な分析ができないという点で、特に新着商品のレコメンドや商品の入れ替わり頻度が高いサイトには注意が必要です。
テキストマイニング(コンテンツベースフィルタリング)
テキストマイニングは、コンテンツベースフィルタリングとも呼ばれ、商品情報(商品名、説明文、ブランド名、カテゴリ名など)を分析して、商品のテキスト属性が類似した商品をレコメンドする手法です。例えば「ウールジャケット」に対して「ウールマフラー」「ウールコート」「テーラードジャケット」などの「ウール」や「ジャケット」といった属性に関連した商品がおすすめされます。
この手法の最大の特長は、商品が登録された段階から一定精度のレコメンドが可能な点です。協調フィルタリングのように行動履歴の蓄積を待つ必要がないため、新着商品でも即座にレコメンドができます。
テキストマイニングの注意点として、商品の登録情報(テキスト)が少なかったり不十分だったりする場合は、適切なレコメンドができないことがあります。
一方で、メタ情報や紹介文などのテキスト情報も活用できるため、文献検索や動画・音楽配信といった大量のコンテンツを扱うライブラリ系サービスでも広く利用されており、商品情報の特性から条件設定できる柔軟性が評価されています。
ハイブリッド・レコメンド
ハイブリッド・レコメンドは、複数のレコメンドロジックを組み合わせることで、より最適で高度なレコメンドを実現する仕組みです。代表的なものに、協調フィルタリングとテキストマイニングを掛け合わせたハイブリッドなレコメンドが挙げられます。
例えば、リピーター顧客には過去の購入履歴から「よく一緒に買われる商品」を提案し、新規訪問者には閲覧中の商品と類似する「関連商品」を表示するといった使い分けが可能です。また、ロジックそれぞれの強み・弱みを考慮し、定番商品は協調フィルタリング、新着商品はテキストマイニングといった使い分けも効果的です。
状況に応じて最適な手法を選択・組み合わせることで、各レコメンド技術の弱点を補完し、より精度の高いレコメンドが実現できるレコメンドロジックです。
パーソナライズド・レコメンド
パーソナライズドレコメンドとは、顧客ごとの購入履歴や閲覧履歴から興味関心を分析し、「あなたへのおすすめ商品」や「あなたにおすすめのブランド」など、個人の嗜好に合わせたレコメンドが可能となります。
ECサイトに再訪問した際、TOPページやマイページにパーソナライズドレコメンドを表示することで、コンテンツを顧客ごとに変更することができ、パーソナライズな接客を実現します。
ルールベース・レコメンド
ルールベースレコメンドは、管理者(サイト運営者やWebサイト設計者)が事前に設定したルールに基づいて商品を推奨する手法です。「パソコン閲覧時に同カテゴリ商品をおすすめ」「デスク購入時にイス商品を表示」など、具体的な条件と推奨商品を意図的に決められます。
実店舗の商品陳列と同様の考え方で、顧客の属性や履歴に関係なく運営戦略に基づいて商品をセットするため、期間限定キャンペーンや特定商品の積極販促に適しています。また「同カテゴリの新着表示」などは実装が容易なため採用されるケースも多くあります。
運営側の意図を直接的に反映できる一方で、適切な設定や運用を怠ると、在庫切れ商品の表示やそのままずっと掲載されてしまったり。新商品の登録がされなかったりといった課題が出てきます。
また、同カテゴリの商品を”こちらもオススメ”といったレコメンドとして表示する設定は比較的容易にシステム設定できますが、商品詳細ページでは協調フィルタリングと比較して今見ている商品との関連性が薄れる可能性があることも理解しておく必要があります。

ECサイトにおけるレコメンド機能のメリット
ECサイトにレコメンド機能を導入することで得られるメリットは多岐にわたります。単純な売上向上だけでなく、サイト全体のユーザビリティ改善や長期的な顧客関係構築にも大きく貢献します。以下、主要なメリットを詳しく見ていきましょう。
クロスセル・アップセルによる客単価向上
商品購入時に、関連する商品を追加で提案することにより、ECサイトでも実店舗の接客のような「ついで買い」「思わず買い」を創出できます。関連商品やセット商品の提案により、1回の購入あたりの購入個数、CVR(コンバージョン率)等を効率的に向上させることが可能です。コーディネート商品や送料無料を狙った低単価商品などのレコメンドが効果的です。
サイト離脱率改善、回遊性・利便性の向上
関連商品や購入履歴、売れ筋ランキング、新着商品など多様な"切り口"でアイテムを提示できるため、顧客の回遊や商品比較がスムーズになり、1訪問あたりの商品閲覧回数が向上します。それにより、サイトの離脱率が改善し、サイトへの満足度が向上します。
リピーターの獲得・顧客満足度向上
パーソナライズをはじめ、適切なタイミング・内容で商品を提案できることから、「自分のことを理解してくれるサイト」という印象を強め、リピート利用を促進します。顧客のLTV(顧客生涯価値)向上にも直結する重要なメリットです。
商品発見の支援とCVR(コンバージョン率)改善
膨大な商品数を抱えるECサイトでは、顧客が求める商品を見つけにくいという課題があります。レコメンド機能により、顧客の興味に合致した商品との出会いを促進し、結果的にCVR(コンバージョン率)の改善が期待できます。

ECサイトへのレコメンド機能の導入・運用方法
レコメンド機能の導入方法は、ECサイトの規模や予算、技術リソースによって複数の選択肢があります。以下、代表的な導入パターンをコストや特徴の観点から整理してご紹介します。
ECパッケージ標準機能の活用
もし、導入されているECシステムに標準でレコメンド機能が付いている場合、初期段階では標準搭載のレコメンド機能を利用する方法が最もリーズナブルです。ただし、高度なカスタマイズや精度向上には限界があり、チューニングや効果測定をする管理画面が付属していないケースが多いので注意が必要です。
レコメンド専門サービスの導入
レコメンド専門サービスは主にSaaS(ASP)型で提供されていることが多いため、比較的低コスト・短期間で、高度なレコメンド専門機能の導入ができます。ビジネス成長や運用負荷に応じて、サービス選択や切り替えもしやすいのが特徴です。中小規模のECサイトに適した選択肢といえるでしょう。
SaaS(ASP)型の場合は、主に初期導入費用と毎月の月額費用が発生します。場合によってシステム面でのサポート、活用するためのコンサルティングサポート、何かしらのカスタマイズやオプションなど、自社に必要なサービスの追加を検討することで最適なレコメンド専門サービスが選択できます。
プライベートDMP/CDPの構築
大規模EC、トラフィックや商品点数が多い場合は、自社データプラットフォームと連携させることで高精度なレコメンドや一元管理も実現できます。データ活用の幅が広がり、より戦略的なマーケティングが可能になります。一方で、レコメンド専門サービスほどの柔軟性がない(サイトにてレコメンドすることに特化していない)ケースもあるため、自社サイトで実現したいこととプライベートDMP/CDPでできることのすり合わせをすることが重要です。
MAのレコメンド機能を利用
レコメンド機能はMA(マーケティングオートメーション)ツールに標準搭載されていることも多く、既にMAを導入している企業であれば、追加の導入コストをかけることなくレコメンド機能を活用できる場合があります。MAのレコメンド機能を利用する場合、顧客データやメール配信などの他のマーケティング機能と連携した統合的な施策展開が可能となり、効率的な運用が期待できます。
フルスクラッチ開発
顧客管理やマーケティングオートメーション等の全体最適を目指す場合、独自開発や他サービス連携による設計も選択肢となります。最も柔軟性が高い反面、開発コストと時間が必要です。
商品間レコメンド以外にも使えるレコメンドロジック
ECサイトのレコメンドには、商品詳細ページで「この商品に関連する(一緒に見ている/購入している)商品はこちら」といった商品ページで商品をレコメンドする以外にも、さまざまな切り口で商品やアイテムを表示できるものがあります。以下の3つのロジックは自動的に表示する仕組みがあり、サイト運営に人手はかけられないけど、コンテンツは充実させたい、そんなお悩みにも対応が可能です。
ランキング
レコメンドシステムが蓄積した行動履歴データを活用することで、多様な切り口でのランキング表示が可能になります。ランキングの種類は、参照するデータによって大きく分かれます。「閲覧ランキング」では最も注目を集めている商品を、「売上ランキング」では実際の購買実績に基づいた人気商品を、「購入ランキング」では購入件数の多い商品を表示できます。
また、集計期間の設定によってもランキングの顔ぶれは大きく変わります。日間ランキングではトレンドや季節要因を反映した商品が上位に表示され、週間・月間ランキングでは安定した人気商品が上位を占める傾向があります。さらに、取り扱い商品の単価帯や商品特性によってもランキング結果は変化します。高単価商品では閲覧数と購入数に大きな差が生まれやすく、消耗品や日用品では購入頻度が高くなるなど、商材特性を考慮したランキング設計が重要です。
このように、単一の「人気商品ランキング」ではなく、サイトの特性や顧客ニーズに応じた多角的なランキング表示により、顧客の商品発見を効果的にサポートできます。
履歴(リマインド)
ECサイトの中で、「最近チェックした商品」や「閲覧履歴」など、そのサイトで直近見た商品が表示されている場合があります。実は、これもランキングと同様に、レコメンドのひとつと捉えることができ、レコメンドエンジン側で表示するケースもあります。
新着アイテム
レコメンドサービスは、定期的にサイトに掲載されるアイテムの情報を取り込んでいます。その中で、初めて取り込まれるアイテムを認識し、「新着アイテム」「新着商品」といったかたちで、それらのアイテムを表示するような仕組みもあります。これも、人手の運用で実現するにはハードルが高い仕組みです。
レコメンドエンジンにおける導入時の注意点
データ蓄積・分析期間の確保
行動分析型ロジックは成果を発揮するまで一定の準備期間が必要です(例えば2~3週間の行動データ蓄積など)。導入初期は効果が限定的でも、継続的な運用により精度が向上していきます。
商品数・データ量が効果に与える影響
商品数が少ない場合や、アクセス数が少ないサイトではバリエーションや精度に限界があります。十分なデータ基盤の構築が効果向上の鍵となります。
適切なタイミングと内容での提案が重要
過度な商品プッシュではなく、"最適なタイミングと内容"での提案が重要です。客単価向上だけでなく、顧客回遊や満足度向上を念頭に設定することが、長期的な成果とブランド価値向上につながります。
継続的な改善・最適化
レコメンド機能は導入して終わりではありません。定期的な効果測定と改善により、より高い成果を実現できます。A/Bテストやデータ分析を通じて、継続的な最適化を行いましょう。
サイト以外のレコメンド活用
レコメンドはECやコンテンツページのみで活用できるわけではなく、サイト上にポップアップ等で表示されるWEB接客ツールの枠の中、メール、LINE、DMなど様々なところに活用することが可能です。
特に、レコメンドメールやLINEでは通常の一括配信のメルマガと異なり、ユーザーごとにおすすめ商品を入れ替えることが可能なため、配信タイミングなども調整することで最適なタイミングで最適な商品をレコメンドできCVR・売上の向上に貢献します。
まとめ:レコメンド機能でECサイトの価値向上を
レコメンド機能は顧客の"今"のニーズに即した提案で、使いやすさと売上拡大、そして中長期のリピーター獲得・ブランド形成に貢献する重要な施策です。
売れ筋ランキングや新着商品など多様な情報表示も自動化でき、サイト運営の効率化にもつながります。自社の目的・規模・予算、そして顧客体験の向上を総合的に考慮して、最適なレコメンド戦略の導入・改善を検討してみましょう。
適切に運用されたレコメンド機能は、ECサイトの競争力強化と持続的な成長を支える重要な基盤となります。
株式会社DGビジネステクノロジー(旧社名:ナビプラス株式会社)では、多種多様なECサイトに対してレコメンドサービスを長年にわたって提供してきた豊富な実績があります。売上向上、CVR改善、顧客満足度向上など、具体的な成果につながるレコメンドシステムの実現をサポートいたします。
ECサイトへのレコメンド導入・改善についてご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。専門スタッフが貴社の課題をお伺いし、最適なソリューションをご提案させていただきます。